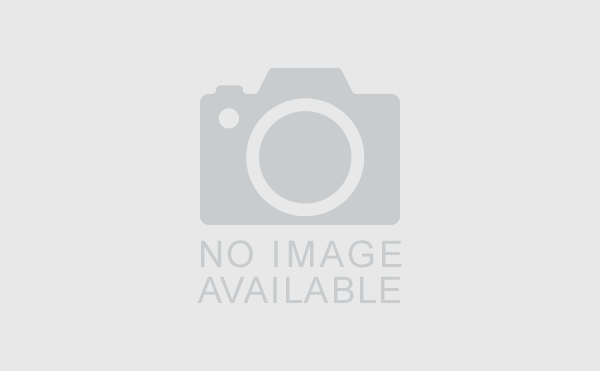Contents
全国で固定資産税の過大徴収が絶えない

固定資産税の過大徴収が問題となった大きな事件は、2014年に発覚した「新座事件」がある。埼玉県新座市が夫婦から27年間にわたって本来の2倍超の固定資産税を徴収していた事件である。今回はこの事件の内容を検証してみました。
固定資産税の過大徴収の「新座事件」とは
- 発端:埼玉県新座市在住の60代の夫婦が、1986年以降約27年間にわたり、本来土地に対して適用すべき「小規模住宅用地特例」の課税がされず、税額が約6分の1の負担軽減対象となるべきところ、多額の固定資産税が課され続けていたことが発覚した。
- 過徴収事実:2013年度には、本来の税額が年額約4.3万円であるところ、実際は11.9万円を徴収。滞納金と延滞金を含めて総額約800万円にのぼり、そのうち延滞金は約6割にあたる。
・発覚の経緯:当該住宅が公売され不動産業者に売却された後、落札業者より税額の異常に気づいて調査が行われ、はじめて過大徴収が判明した。
経過・行政対応は?
・返還措置:市は法令に基づき、1994年まで過去20年間を遡って、過徴収された税金と延滞金など約240万円を返還したものの、家屋は戻らかった。
・謝罪と説明:須田市長は「いかなる理由でも許されないこと」と深く謝罪し、住民への丁寧な対応と改善を約束した。
・全市調査の着手:固定資産税調査特別班を設置し、市内全物件(約6万6千筆)を対象に現地確認と課税見直しを開始。調査の結果、土地・建物を含め過徴収件数は 約 3,000 件、還付総額は約 8.4 億円に達したと報告された。
影響と問題点
- 住民の生活への重大な影響:本来支払える水準であれば継続可能だった納税が、高額な延滞金で支払い不能に。結果、公売による家屋喪失という重大な被害に至ったことが社会的に大きな反響を呼んだ。
- 行政のチェック体制の欠如:地方税法により年1回の現地調査義務があるにもかかわらず条件違反となり、市税務課が27年にわたり実地調査を怠っていた点が問題視された。
・制度の複雑さと説明責任:課税制度の繁雑さと、不明瞭な説明態勢のため納税者が自身の税額を検証しづらく、誤徴収が長期間見逃された一因となった。
今後の対策
・毎年のように過大徴収が発生:長期にわたって気づかないまま過大徴収がされ続けている不動産所有者が多い。どのように対策したら良いのだろうか?
・総務省の調査:総務省調査によると、特にミスが発生しやすいポイントとしては、土地と家屋で「評価額」の算定ミスが最も多い。次いで、土地は「減税特例」の適用忘れ、家屋は 「取り崩し」の反映忘れが多い。
・一般人ができること:ミスを発見することは困難なので、税理士や不動産鑑定士などのプロのサポートを受けて税額のチェックを行うしかないのが現状のようだ。