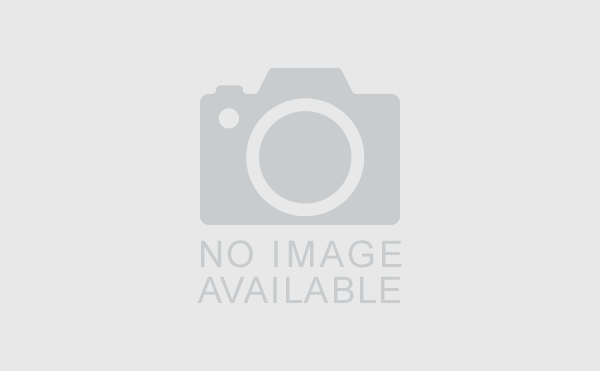変動型住宅ローンの金利の「5年ルール」の注意点とは

Contents
変動型住宅ローンの金利の「5年ルール」とは
住宅ローン(変動金利・元利均等返済方式)に適用されるルールです。金利が上昇しても、毎月の返済額は直ちには変わらず、原則5年間は据え置きとなります。
金利上昇があったとしても、すぐに返済額が変わるわけではありません。返済額の見直しは「5年ごと」に行われます。
したがって、「金利が上がった時点から必ず5年間固定」という意味ではなく、「前回の見直しから次の5年目まで同額が続く」という解釈が正しいです。
5年後の見直し時に、急激に返済額が増えるのを防ぐため、最大でも直前の返済額の125%までしか上がりません。そのため「激変緩和」と呼ばれます。
必ず5年間返済額が変わらないのではなく、ケースによっては数か月で変わる?
「金利が上がった日から5年間返済額が変わらない」のではなく、
→「見直しのタイミングが5年ごとなので、その間は同じ返済額が続く」
ポイントは「金利の見直し」と「毎月返済額(返済額)の見直し」は別イベント、ということです。
そのうえで「5年ルール」は返済額の見直しタイミングを5年おきにする決まり、という意味です。
つまり・・・ケースによっては数か月で返済額が上がることも想定する
金利は頻繁に動く
変動金利は多くの銀行で半年ごと(例:4月・10月)に見直されます。
ただし金利が上がっても毎月の返済額はその場では変わりません。
- 返済額は5年間“据え置き”
返済額(毎月いくら払うか)を実際に変えるのは5年に一度。
つまり「前回返済額を決めた(または変更した)月から60か月間は同じ額が続く」ということです。
※「金利が上がった日から5年間固定」ではありません。「基準は“前回の返済額見直し日」です。 - その間なにが起きている?
返済額は一定でも、内訳(利息と元金の配分)が変わります。
金利が上がるほど、同じ返済額の中で利息の取り分が増え、元金の減りが遅くなります。
金利が大きく上がりすぎると、まれに「未払利息(元金が減らない/増える)」が発生することも。
総返済額が増加する可能性とその他のリスク
- 総返済額が増加する可能性
5年ルールにより支払う利息が優先されて元金返済が後回しになるため、結果として総支払利息が増える傾向にあります。 - 未払い利息(未払利息)の発生リスク
金利が大幅に上昇すると、返済額に利息の支払いが追いつかず、元金が減らないばかりか未払利息が発生する場合もあります。
こうした利息は後日に繰り延べられ、最悪の場合、返済終盤に一括請求されることもあり得ます。 - 適用されるのは「元利均等返済」の場合のみ
元金均等返済方式では、毎月の返済額自体が変動するため、5年ルールや125%ルールはそもそも適用されません。 - 実際に125%ルールが発動する状況は稀
シミュレーション結果では、極端な金利上昇(例:20%以上)にならない限り、125%ルールの上限に達することは現実的にはほとんどないとされています。
よって、「125%ルールがあるから安心」には一定の注意が必要です。
「金利のある世界」で今後の考え方
「安心」と「コスト」のバランスを理解しましょう。
5年ルール・125%ルールによって、当面の家計は安心できますが、それはあくまで元金返済の遅延と引き換えです。総返済額が増える可能性を十分に熟知することが重要です。
金利上昇への備えは積極的に!
繰り上げ返済や金利タイプの見直し(必要に応じて固定金利への変更検討)など、金利上昇時の対策をプランに組み込みましょう。
返済方式の選択も再検討の余地あり。
元利均等返済で5年・125%ルールの恩恵を受けたいか、元金均等で早期に元金減少を進めたいか、ライフプランに応じて最適な返済方式を選択することが大切です。