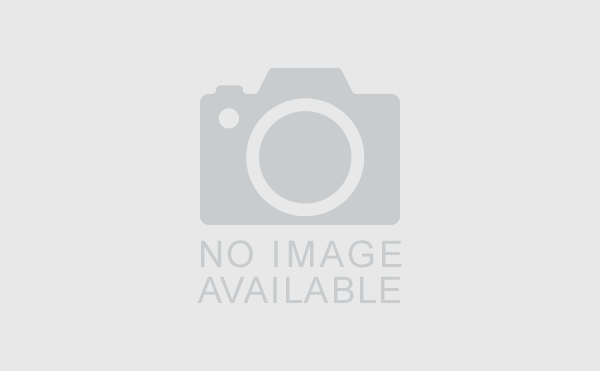事案の概要

ふるさと納税にポイントが付与されることが10月1日から禁止になってから、「ポイントがもらえなくなるのは残念」という声や「制度の本旨に立ち返る好機」と様々な意見があるが、ポイント付与廃止後もふるさと納税は継続したいとの答えた人は8割超を超えました。
ふるさと納税は地域を応援しながら返礼品も楽しめる制度として人気ですが、実は思わぬ「落とし穴」があります。それは 返礼品が税法上「一時所得」とされ、課税対象になる という点です。今回は、返礼品の価値をどう算定するのかをめぐって争われた裁判を紹介します。
ある女性は2018年までの2年間に、全国の延べ約110自治体に対して490件ものふるさと納税を実施しました。寄付総額は約660万円。食品や酒、宿泊券など多様な返礼品を受け取っていました。
しかし、確定申告の際には給与所得などは申告したものの、返礼品の分は一時所得として申告しませんでした。
税務署の指摘と納税者の主張
税務署は女性に対し、返礼品の価値を「自治体が調達に支出した金額」と定義。その結果、490件分で約280万円にのぼると算定しました。このうち特別控除(50万円)を超える部分が課税対象となり、所得税40万円超の追徴課税を通知しました。
それに対し女性は「返礼品の価値はインターネットなどでの最安値に基づいて判断すべき」と反論。また、総務省が自治体に対し「返礼品は寄付額の3割以下」とするルール(いわゆる3割ルール)を示していることを挙げ、「その基準を信じていたのに不意打ちだ」と主張しました。さらに、自治体ごとに調達価格を確認するのは納税者にとって過大な負担だとも訴えました。
裁判所の判断
横浜地裁(2023年2月)
「納税者は自治体に確認するなどして適正な時価を把握し、申告する必要がある」として、税務署の算定方法を追認。大きな労力を伴っても「当然の負担」と判断しました。3割ルールについては「税務当局の公式見解ではない」とし、納税者の主張を退けました。
東京高裁(2023年12月)
一審を支持して控訴を棄却。
最高裁(2024年5月)
上告を棄却し、女性の敗訴が確定しました。
この判決で明らかになったのは、ふるさと納税の返礼品については 「自治体の調達価格」=課税の基準 になるということ。利用者が考える「市場価格」や「3割ルール」は、課税に直接影響しないという点です。
つまり、返礼品をたくさん受け取った場合、特別控除(50万円)を超えれば課税される可能性が高いということ。申告漏れを避けるためにも、寄付を多数行う際には返礼品の価値をしっかり把握しておく必要があります。
ふるさと納税は地域を応援できる制度ですが、返礼品は「おまけ」ではなく、税務上はれっきとした「一時所得」となります。今回の裁判を通じて、制度を利用する際は 「寄付額」だけでなく「返礼品の課税リスク」 にも注意することが重要だと分かります。