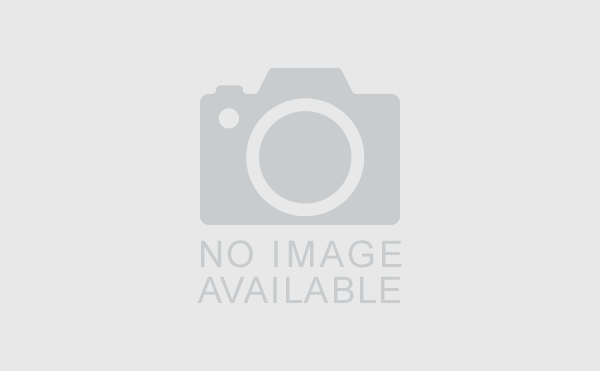変動金利の5年間ルール
変動金利型住宅ローンには、返済額の急激な増加を防ぐために「5年ルール」が設けられていることがあります。金利が変動しても、返済額の見直しは5年ごとに行われ、それまでは毎月の返済額が変わらない仕組みです。ただし、金利が上昇すると、返済額に占める利息の割合が増え、元本の減りが遅くなる可能性があります。以下の理由から導入されています。
家計の安定性の確保
金利が上昇した場合に返済額が急激に増加すると、家計が逼迫し、延滞や債務不履行のリスクが高まります。これを防ぐため、返済額の見直しを一定期間(5年間)に限定しています。
金融機関のリスク管理
住宅ローンが貸し倒れになるリスクを軽減し、長期的な回収計画を安定化させることが目的です。
借り手心理の安定
借り手に過度の不安を与えないことで、ローン利用のハードルを下げ、金融市場全体を活性化させる効果があります。
変動金利の125%ルール
返済額の見直し時に、前回の返済額の1.25倍(125%)を超えて増加しないよう制限するものです。例えば、前回の返済額が10万円であれば、次回の見直し後の返済額は最大で12万5,000円までとなります。
「125%ルール」が実際に適用された事例については、過去に大きな金利上昇がなかったため、日本では一般的に適用されたケースは少ないとされています。しかし、以下の背景や理由から適用可能性が議論されています。
- 低金利環境の長期化
日本では1990年代以降、超低金利政策が続いており、住宅ローンの変動金利も安定して低水準にとどまっています。このため、返済額の急激な増加を引き起こすような金利上昇が発生していません。 - 金利の変動幅が小さい
変動金利型住宅ローンの基準となる短期プライムレートは、過去数十年間にわたり大きな変動がなく、借り手にとって「125%ルール」を適用する必要性が生じていないケースが多いです。 - 金融機関の調整対応
金利上昇時には、金融機関が返済プランの見直しや借り換え提案を行うことで、125%ルールが正式に適用される前に問題が解決する場合もあります。
「5年間ルール」と「125%ルール」の注意点
これらのルールにより、返済額の急増は抑えられますが、金利上昇時には元本の減少が遅れ、最終的な総返済額が増加する可能性があります。また、利息が返済額を上回ると「未払利息」が発生し、最終的に一括返済を求められることもあります。そのため、金利動向に注意し、繰上げ返済などで元本を減らす努力が重要です。一部の金融機関では、5年ルールや125%ルールを設けていない場合があります。例えば、ソニー銀行、新生銀行、PayPay銀行(旧ジャパンネット銀行)などが該当します。これらの銀行では、金利変動に応じて返済額が随時見直されるため、金利上昇時には返済額が増加するリスクがあります。変動金利型住宅ローンを選ぶ際は、各金融機関のルールを確認し、将来の金利変動リスクを十分に考慮することが大切です。